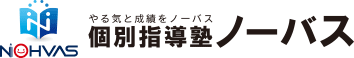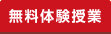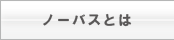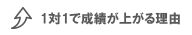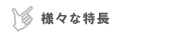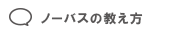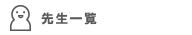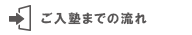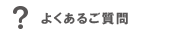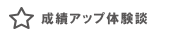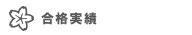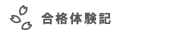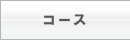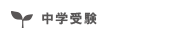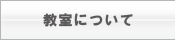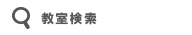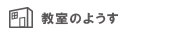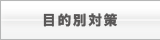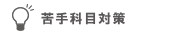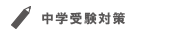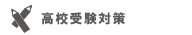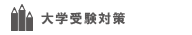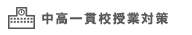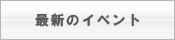2012年9月のお知らせ
彼女は存在しない
こんにちは。
講師の下宮です。
徐々に涼しくなってきましたね。
季節の変わり目。体調を崩しやすい時期なので十分に気をつけましょう。
突然ですが、みなさんは1ヶ月でどれくらいの本を読みますか?
僕は3、4冊くらいでしょうか。
大学までの通学中、電車の中ではたいてい本を読んでいます。
せっかくなので最近僕が読んだ本の中の1冊をみなさんに紹介したいと思います。
「彼女は存在しない」
これがその本のタイトルです。
浦賀和宏著の作品です。
最近、評判になっている本なので、もしかしたらみなさんの中にも読んだことのある人がいるかもしれません。
ちょうど今この本を読んでいる!という人がいるかもしれないので、あまり内容は言えませんが、この本を読んでいるとき、僕の頭には
「彼女」とは誰のことなのだろう。
そして、その「彼女」が「存在しない」とはどういうことなのだろう。
ということが常にありました。
しかしその答えは一向にわかりません。
最後の10ページで全ての謎が解けました。
その結末を知ったとき、思わず「やられた」と思ってしまいました。
これほど最後まで謎が多い作品は正直、初めてではないかと思ってしまうほどでした。
この本の帯にはこう書かれています。
「伏線が1つに収束するとき、物語は悲痛な結末を迎える」
複数あった伏線が1本にまとまる瞬間がラスト10ページで訪れます。
その結末を予想しながら読み進めると面白いかもしれませんよ。
少しでも興味を持った人は読んでみてはどうでしょう。
絶対に期待を裏切らないですよ。
さて、僕は次の本にいきたいと思います。
次は、
「サッカーボーイズ」です。
みなさんもお薦めの本あったら是非、教えてくださいね。
松戸校日記 [2012-09-29]
俺がルールだ!
こんにちは。講師の鈴木です。
つい先日塾で斉藤先生と前回ブログで書いた竹島、尖閣諸島や北方領土などについて熱く議論していました(笑)
その時国際法の話もして、面白いと言われた話題を少し紹介します。
国際法という簡単に言ったら世界のルールですけれど、これには二通りあります。成文法と慣習法です。一言で言うとちゃんと文に書かれている法律と書かれていない法律です。
書かれてない法律ってなんだ?と思うと思います。それは日本の憲法だとか刑法のように戦争をしてはいけない、とか人を殺してはいけないだとかはっきりと六法全書といったものに書かれていない、決まっていない法律で今までの習慣を法律とすることです。例えば学校や部活で裏校則とか暗黙の了解とかあったりしますよね。それみたいなものだとイメージしてください。(※だいぶ軽く表現しています)日本の法律ではそのような慣習法は認められていませんが、イギリスの法律はむしろ慣習法です。びっくりですよね。
じゃあどうやって国際法での慣習法というのはできるのか?
それはこれが当たり前だ、と思わせることと、いろんな国にやってもらうことなのです。
例えば国同士で戦争はしてはいけないということは慣習法です。(成文法でもありますが)いろんな国がそれは当たり前だと思っていることと、勝手に戦争を始めなくなったことが理由です。
前回海も含めた時の日本の広さは〜という話をして、排他的経済水域に触れました。昔この排他的経済水域と大陸棚についてはみんなの思う「法律」に何にも書かれていなかったのです。しかし、排他的経済水域についてはケニアといったアフリカが、大陸棚はアメリカがこれは俺のものだ!と主張して、(※だいぶ軽く表現しています)他の国がじゃあ俺もここの海は俺のもの!とやるようになって(※だいぶ軽く表現しています)慣習法になり、いまでは成文法にもなっています。
だから慣習法というのは言葉悪く表現するとごり押しした者勝ちなのです。だから国際的な場では「俺がルールだ!」と言って他の国もやるようになってしまったら本当にルールになってしまうのです。(※だいぶ軽く表現しています)
今回いろいろ説明しましたが、かなりかる〜く表現しているのであまり鵜呑みしないでくださいね(^^;)では今回はこのへんで。
松戸校日記 [2012-09-28]
授業中にたまにするお話 過去編
松戸校講師の芹川です。
今日は前に書いた「授業中にたまにするお話」の続きです。
この記事は、9月26日現在「松戸校の役に立ったページランキング」の第3位になっています。自分が書いたものに多くの人が興味を持ってくださり、嬉しいです。さて、今日はそのお話の過去編ということで、自分の得意科目である「生物」の歴史を交えて書きたいと思います。前回の内容と重複するところもあるのでもう一度「授業中にたまにするお話」を読み返すことをおすすめします。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
さて、メンデルから始まった遺伝学は長年の研究により、今日の遺伝子組換え技術まで発展しました。その是非はともかく、その発展の主役はまぎれもなく、生物の遺伝情報を担うDNA(デオキシリボ核酸)と呼ばれる物質にほかなりません。この内容は最近では中学生でも扱う内容です。
では、そのDNAはどのような「かたち」をしているのか。この答えは高校で扱う内容です。それはかつて科学者をはじめとする多くの人の関心を集め、しかし彼らの英知と膨大な時間を持ってしても答えを導きだすことは困難でした.
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「2重螺旋構造」
2つの相補なDNA鎖が互いに絡み合い、そして螺旋を描く。世紀の発見とも言われるその答えは2人の科学者によって導かれました。誰もがその発見の偉大さを認め(2人はノーベル賞を受賞しています)、それ以上に生物が持つ美しさに魅了されました。なぜ、その2人は多くの科学者が挑んでは破れていった難問を解き明かすことができたのか。他の多くの科学者が関心を持ちました。それは彼らの聡明な頭脳と洗練された実験手法によるところがもちろん大きいのですが、その1人曰く。
「実に簡単なこと。目、耳、手、足。生物にとって大切なものは2つあり。対をなしている」
過去の人の話なので本当に言ったかかどうかわかりませんが、しかし説得力のある言葉です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「考える力こそが勉強に大切な力だ」
このフレーズはだれもが聞いたことがあり、聞き飽きたことでしょう。確かにそのとおりなのでしょうが、考えることだけが勉強に必要なことなのでしょうか。その大切な物には対をなす相方はいないのでしょうか。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
私が思う「考える力」。
それは物事のひとつひとつの意味を理解し、それを並べ新たな発見に至る力です。帰納法とも呼ばれるその方法は、砂を少しずつ積み重ねて下から城を作る方法に似ています。
しかし、城を上から作る方法もあります。大雑把に目標に立て、後に修正を加えて達成する。この演繹法こそが考える力と対をなす、勉強に大切な力だと思います。それはどのような力か。砂が入ったバケツを引っくり返し、余計な部分を削り城を築く。このとき必要なことは細部にとらわれないことです。バケツをひっくり返す前にで門の形、城内の構造にこだわっていてはこの方法は使えません。それよりも、とにかく目標に向かって突き進むことが必要であり、ある意味「鈍い」ことが求められます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「考える力」がある人のことを「鋭い」と形容することがあります。しかし、勉強においてすべてを理解するには「鋭さ」だけではカバーできません。なぜならその「鋭さ」を超え、疑問点が出てきたときに立ち止まってしまうからです。そのような場合、多少の疑問点はおいて、とりあえず突き進むことも大事です。そしてそのとき、必要とされるのは「鋭さ」ではなく「鈍さ」です。
今まで,塾の講師として短いとは言えない時間を過ごしました。いわゆる勉強ができる人というのは「鋭さ」よりもむしろ良いい意味での「鈍さ」を持っていたように思います。逆に、勉強が苦手な人は物事を「鋭く」考えすぎてしまい、結果諦めてしまう傾向がありました。立派な城が築かれるのは「鋭さ」と「鈍さ」が互いに絡み合い、美しい螺旋を描くときだと思い、あの記事を書きました。
何かの参考になれば幸いです。
松戸校日記 [2012-09-27]
秋のことわざ
こんにちは、講師の高野です(-ω-)ノ
もう9月も終りに近づき、あと一週間もしないうちに10月になりますね…。
気温もだいぶ低くなってきて、秋が来るな〜といった感じです。
さて、突然ですがクイズです!
○に漢字を入れて以下の「秋」が入ることわざを完成させて見て下さい!
1.天高く○肥ゆる秋
秋の快適な気候の素晴らしさのこと。
2.女心と秋の○
変わりやすい秋の空模様のように、女性の気持ちは移り気だということ。
3.物言えば○寒し秋の風
人の悪口を言えば、なんとなく後味の悪い思いをするというたとえ。
また、余計なことを言えば災いを招くというたとえ。
4.秋○○は嫁に食わすな
ナスは体を冷やすので食べ過ぎるのは体に良くないという意味。
5.一葉落ちて○○の秋を知る
わずかな前兆を見て、後に起きることを予知することのたとえ。
6.一日○秋
非常に待ち遠しいことのたとえ。
7.秋の日は○○落とし
日がどんどん短くなっていくようす。
8.秋の○は笛に寄る
恋に身を滅ぼすたとえ。また、弱点につけこまれて利用されやすいことのたとえ。
秋は色々なことわざがありますね…。
皆さんはいくつ分かりましたか?
まぁ、高校受験生ともなれば全問正解であたりまえでしょうが…(´_ゝ`)
一応答えも書いておきますね。
1.馬2.空3.唇4.茄子5.天下6.千7.釣瓶8.鹿
では今回はこれにて(´・ω・)ノ
松戸校日記 [2012-09-26]
重要なお知らせ
 明けましておめでとうございます
明けましておめでとうございます

明けましておめでとうございます旧年はお世話になりました個別指導塾ノーバス松戸校は本日1/5(月)から授業を再開しております。今年も一緒に頑張っていきましょう。...
[2026-01-05]
最近のお知らせ
 年末・年始のお知らせ
年末・年始のお知らせ

いつもお世話になっております。ノーバスでは、12月28日(日)〜1月4日(日)までお休みをいただいております。期間中は自習室もご利用いただけませんので、ご注意ください。お休み期間中にいただいたご連絡につきましては、1月5日(月)の業務開始後、順次お返事させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。塾長 矢嶋...
[2025-12-29]
 入塾金無料キャンペーンは残り僅かとなります
入塾金無料キャンペーンは残り僅かとなります

お世話になっております。個別指導塾ノーバス松戸校です。入塾金無料のキャンペーンは12/29(月)までとなります。1月に入試が始まり、2月に学年末テストが実施され、冬は勉強の集大成になります。この冬休みで今までの復習やこれからの予習をしていき、進級進学後のための力にしましょう。冬期講習も受け付けております。冬期講習もいつ...
[2025-12-24]
 年内の受付は12/29(月)までです
年内の受付は12/29(月)までです

いつもお世話になっております。入会のお問い合わせを多数いただき、誠にありがとうございます。年明けから入会をお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、スムーズに授業をスタートさせるためにも、年内にお手続きを済ませていただくことをお勧め致します。ノーバスは完全1対1の授業ですので、個人に合わせた様々なご要望にお応えすることが...
[2025-12-18]












 お知らせ全て
お知らせ全て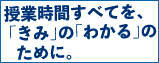



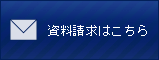
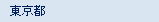
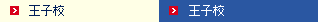
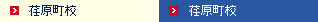
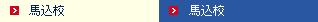
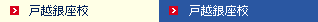
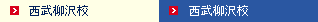
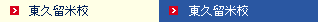
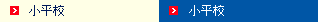
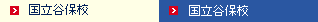
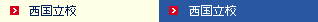
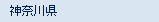
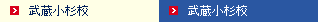
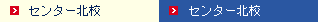
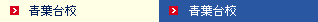
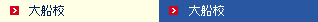
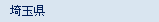
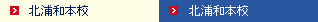
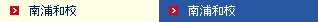
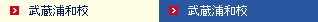
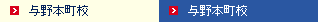
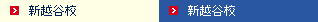
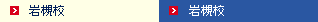
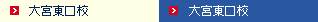
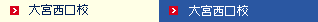
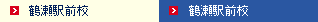
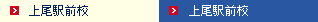
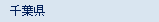
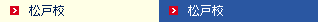
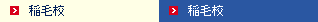
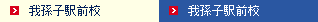
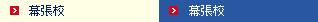
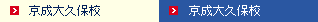
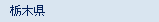
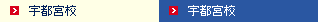
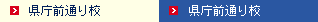
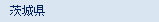
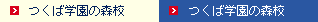
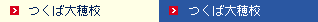
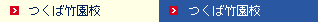
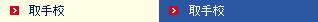
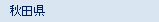
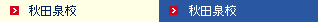
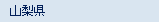
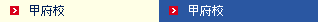
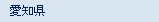
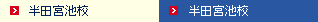
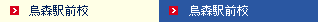
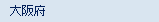
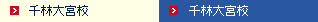
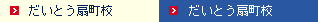
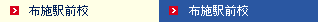
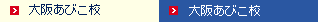
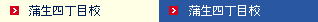
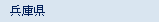
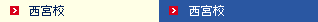
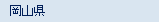
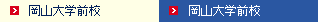
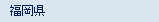
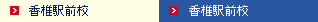
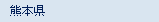
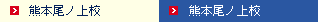

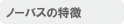

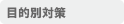




 2025-11-04
2025-11-04 2025-03-06
2025-03-06 2025-02-28
2025-02-28 2024-09-02
2024-09-02 2024-03-08
2024-03-08 2023-09-11
2023-09-11 2023-09-05
2023-09-05 2023-08-07
2023-08-07 2022-12-08
2022-12-08 2022-09-27
2022-09-27 2022-09-01
2022-09-01 2022-06-17
2022-06-17 2022-06-17
2022-06-17 2022-05-16
2022-05-16 2022-05-09
2022-05-09 2022-02-25
2022-02-25 2021-11-19
2021-11-19 2021-09-01
2021-09-01 2021-05-06
2021-05-06 2026-01-12 岡山大学前校
2026-01-12 岡山大学前校 2026-01-12 荏原町校
2026-01-12 荏原町校 2026-01-12 与野本町校
2026-01-12 与野本町校 2026-01-12 取手校
2026-01-12 取手校 2026-01-11 南浦和校
2026-01-11 南浦和校 2026-01-10 武蔵浦和校
2026-01-10 武蔵浦和校 2026-01-10 王子校
2026-01-10 王子校 2026-01-10 稲毛校
2026-01-10 稲毛校 2026-01-10 宇都宮校
2026-01-10 宇都宮校 2026-01-10 熊本尾ノ上校
2026-01-10 熊本尾ノ上校